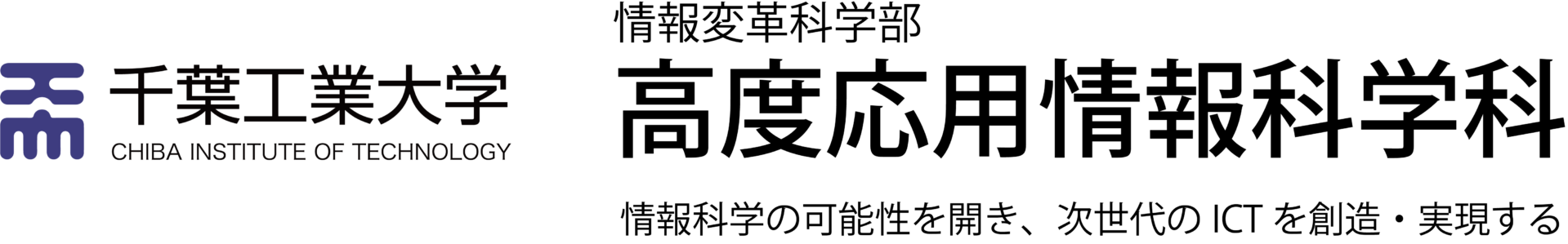高度応用情報科学科では、情報処理技術の基礎から応用まで幅広く学習します。ここで、各学年での学びの概要は以下の通りとなります。
【1年次】コンピュータや情報処理技術の基礎を学びます
情報処理技術を学ぶための基礎となる数学を学ぶとともに、情報処理技術の基礎を理解し、どのような応用があるのかを学修します。また、同時にプログラミングを含む演習を行います。
【2年次】情報処理技術の役割とその応用方法を理解します
専門科目や教養科目の基礎を固めるとともに、情報処理技術の活用・応用方法に重点を置いて学びます。データサイエンスやネットワーク技術を学修し、引き続きプログラミングを含む演習などを行います。
【3年次】専門科目により広範囲の情報処理技術及びその応用を身に付けます
セキュリティ、クラウド、ネットワーク、IoT、金融工学、情報倫理などに関連する幅広い技術を講義及びさまざまな実験を通して身につけます。
【4年次】卒業研究に取り組み、新しい価値を創造する力を養います
学びの集大成としての卒業研究に取り組みます。各自のテーマについて、理論や実験などを重ねながら成果をまとめ、プレゼンテーションを行います。これまで学んだ知識を確実なものとし、社会で役立つ「+α」の提案ができる応用力を磨きます。
ここで、1年次から4年次までに学ぶことのできる専門科目の一覧を次の図に示します。ここで、赤字で書かれた科目は演習、実験科目を表し、コンピュータ等を利用して実践力を身に付けます。
-1-1024x542.png)
スマートフォン向けアプリ開発を例にした学びの概要
本学科のカリキュラムを身近な情報端末であるスマートフォン(以下、スマホ)を例に紹介します。スマホ上で動作するアプリケーション(以下、アプリ)には様々な技術が使われていますが、スマホ単体で見ても、アプリケーション技術の開発に必要なプログラミング技術、スマホに付随するセンサーや音・映像などの情報メディア、利用者の視点から情報システムを考える人間工学など様々な要素について学びます。また、スマホを取り巻く通信環境についても広くカバーします。スマホ上で動作するアプリには、通信環境が無くても動作するネイティブアプリ、インターネットからプログラムやデータをやり取りして動作するWebアプリケーション(以下、Webアプリ)があります。このWebアプリは、スマホやPCなどのハードウェアの制約を超えて動かすことができるため、クラウドコンピューティングの主要技術に位置付けられています。本学科では、スマホで動作するWebアプリの実現に必要なクラウドコンピューティングの主要技術について、その基礎から応用まで幅広く学習することができます。
ここで、Webアプリについて詳しく見てみます。まず、プログラミング的な側面から見てみると、Webアプリは、スマホ上で動作するフロントエンド、サーバー側で動作するバックエンドに分かれます。通常、これらの環境では異なるプログラミング言語が利用されます。そのため、本学科ではプログラミングに関する応用力を高めるため、クラウド環境で利用される複数のプログラミング言語を利用してシステム開発を学びます。さらに、プログラムの実行環境となるインフラストラクチャの構築・利用方法も合わせて学びます。具体的には、ネットワークの設計・構築技術、サーバ構築技術、OSの利用方法、仮想計算機の作成・構築・管理など、クラウドコンピューティングの基礎と応用などについて学びます。
次に、Webアプリをデザイン的側面から考えます。Webアプリでは、開発コスト低減の観点から、デスクトップやタブレット、スマホなど大きさの異なる画面に対してデザインを自動的に変化させるレスポンシブルデザインが採用されることも多くなっています。さらに、利用しやすいユーザーインターフェース(UI:User Interface)や、利用者のユーザー体験(UX:User eXperience)の重要性も高まっています。本学科では、ユーザー体験の向上に結びつく人間的側面からのアプローチとして、人間工学、行動科学分析等の授業も用意しています。
最後にWebアプリの裏側にあるビッグデータについて考えます。近年、モノのインターネットと呼ばれるIoT(Internet of the Things)が注目されています。IoTでは、潜在的に情報を有する物品、空間、装置へセンサーや演算機能、通信機能などを取り付けて、インターネット上で大量の情報が管理されます。例えば車の渋滞情報や電車の混雑情報、天候情報などへの応用が挙げられます。本学科では、IoTシステム、IoTシステム構築実験などの科目でIoTシステムに必要な知識と技術を修得し、IoTシステムが収集したデータを分析する際の基礎となるデータサイエンスについて学ぶことができます。また、IoT技術を支えるインフラストラクチャ技術として、クラウドコンピューティング、クラウド構築演習、サイバーセキュリティ、サイバーセキュリティ実験などの学修も行えます。